こうして大事なことがもう一つわかった。何とその子の住む星は、一軒の家よりもちょっと大きいだけなんだ!

といっても大袈裟に言うほどのことでもない。ご存知の通り、地球、木星、火星、金星みたいに名前のある大きな星の他に、望遠鏡でもたまにしか見えない小さなものも何百倍とある。例えばそういったものが一つ、星博士に見つかると、番号で呼ばれることになる。〈小惑星三二五〉という感じで。
ちゃんとした訳があって、王子くんお住まいの星は小惑星B六一二だと僕は思う。前にも一九〇九年に、望遠鏡を覗いていたトルコの星博士がその星を見つけている。
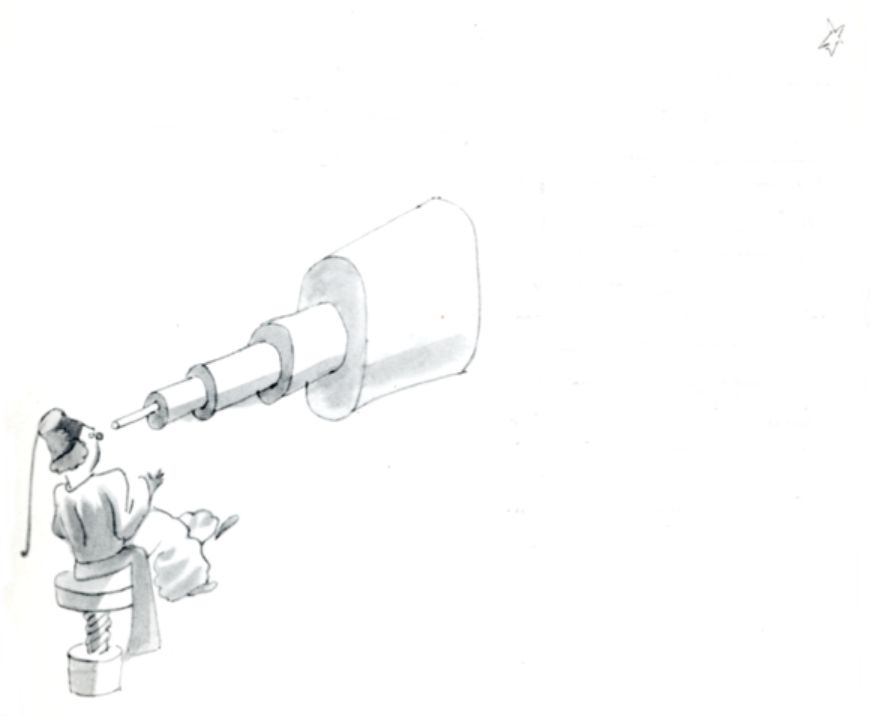
それで世界星博士会議というところで、見つけたことをきちんと発表したんだけど、身につけている服のせいで信じてもらえなかった。大人のひとって、いつもこんなふうだ。

でも小惑星B六一二は運がよくて、そのときの一番偉い人がみんなに、ヨーロッパ風の服を着ないと死刑だぞ、というお触れを出した。一九二〇年にその人は、お上品な召し物で発表をやり直した。すると今度は、どこも誰もがうんうんと頷いた。
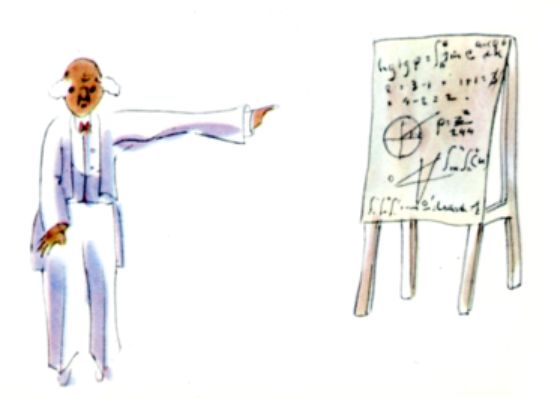
こうやって小惑星B六一二のことをいちいち言ったり、番号の話をしたりするのは、大人のためなんだ。大人のひとは数字が大好きだ。この人達に新しい友達ができたよといっても、中身のあることは何一つ訊いてこないだろう。つまり、「その子の声ってどんな声? 好きな遊びは何なの? チョウチョは集めてる?」とは言わずに、「その子いくつ? 何人兄弟? 体重は? お父さんはどれだけ稼ぐの?」とか訊いてくる。
それでわかったつもりなんだ。大人のひとに、「すっごい家、見たよ、バラ色のレンガでね、窓のそばにゼラニウムがあってね、屋根の上にも鳩がたくさん……」と言ったところで、その人達はちっともその家のことを思い描けない。こう言わなくちゃ。「十万フランの家を見ました」すると「おお素晴らしい!」とか言うから。
だから僕がその人達に、「あのときの王子くんがいたって言い切れるのは、あの子には魅力があって、笑って、羊をおねだりしたからだ。羊をねだったんだから、その子がいたって言い切れるじゃないか」とか言っても、何言ってるの、と子供扱いされてしまう! でもこう言ったらどうだろう。「あの子の住む星は小惑星B六一二だ」そうしたら納得して、文句の一つも言わないだろう。大人ってこんなもんだ。恨んじゃいけない。大人のひとに、子供は広い心を持たなくちゃ。
でももちろん僕達は、生きることが何なのかよくわかっているから、そう、番号なんて気にしないよね! できるならこのお話を、僕は御伽噺風に始めたかった。こう言えたらよかったのに。
「むかし気儘な王子くんが、自分よりちょっと大きめの星に住んでいました。その子は友達が欲しくて……」生きるってことをよくわかっている人には、こっちのほうがずっともっともらしいと思う。
というのも、僕の本をあまり軽々しく読んで欲しくないんだ。この思い出を話すのは、とてもしんどいことだ。六年前、あの坊やは羊と一緒にいなくなってしまった。ここに書こうとするのは、忘れたくないからだ。友達を忘れるのは辛い。いつでもどこでも誰でも、友達がいるわけではない。僕もいつ、数字の大好きな大人のひとになってしまわないとも限らない。だからそのためにも、僕は絵の具と鉛筆を一ケース、久しぶりに買った。この年でまた絵を描くことにした。最後に絵を描いたのは、中の見えないボアと、中の見えるボアをやってみた六歳のときだ。当たり前だけど、なるべくそっくりにあの子の姿を描くつもりだ。うまく描ける自信なんてまったくない。一つ描けてももう一つは全然駄目だとか。大きさもちょっと間違ってるとか。王子くんがものすごくでかかったり、ものすごくちっちゃかったり。服の色も迷ってしまう。そうやってあれやこれや、うまくいったりいかなかったりしながら頑張った。もっと大事な細かいところも間違ってると思う。でもできれば大目に見てほしい。僕の友達は一つもはっきりしたことを言わなかった。あの子は僕を、似た者同士だと思っていたのかもしれない。でもあいにく僕は、箱の中に羊を見ることができない。ひょっとすると、僕もちょっと大人のひとなのかもしれない。きっと年をとったんだ。

