太宰治が、強烈な知人についておもしろく語っている「親友交歓」という短編が好きで、私は年に一回ぐらいはふと思い出して読んだり、人に勧めたりしている。このたび知人が「この文章には読点が多すぎる」と言うのを耳にした。もう一度読んでみると確かに多い。読むに差し障るほどではないが、酔狂にこの知人の不満に応えるために、試みに読点を今の読み物風に打ち代えてみた。以下、その試みの結果である(底本は青空文庫)。
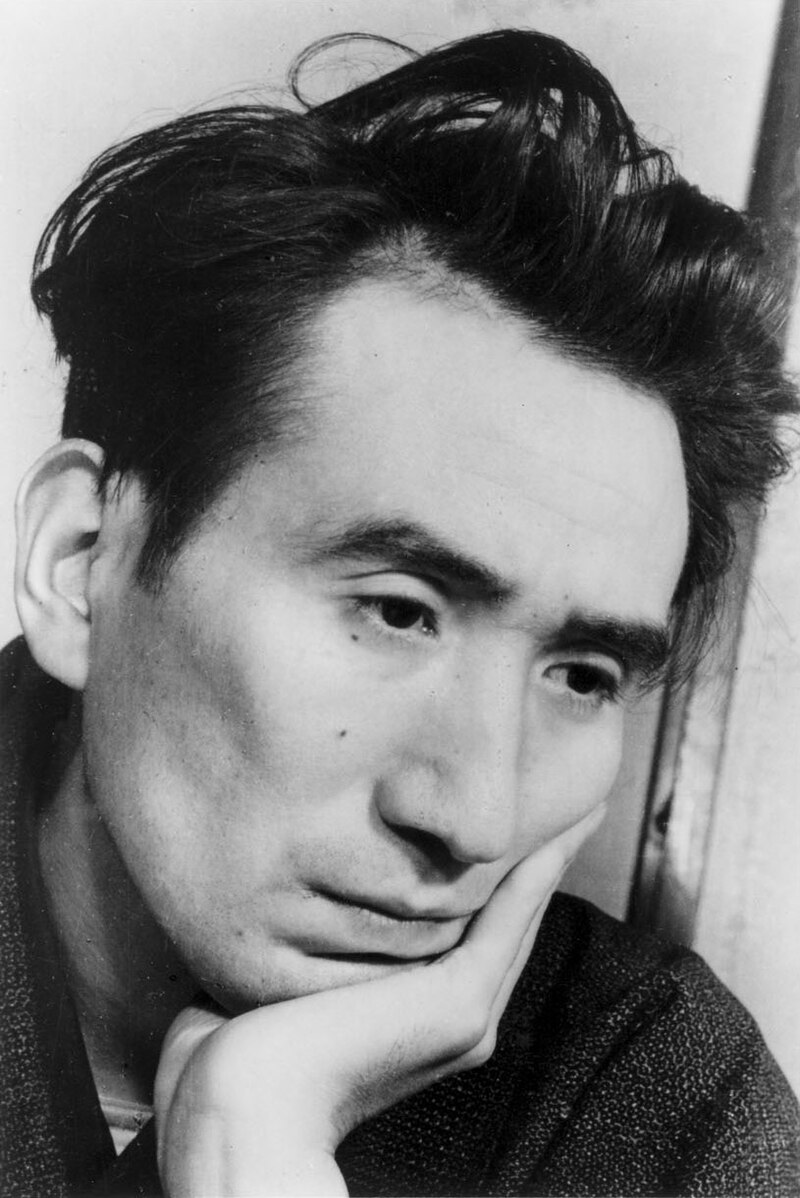
昭和二十一年の九月のはじめに、私は或る男の訪問を受けた。
この事件はほとんど全くロマンチックではないし、またいっこうにジャアナリスチックでも無いのであるが、しかし私の胸に於いて私の死ぬるまで消し難い痕跡を残すのではあるまいかと思われる、そのような妙にやりきれない事件なのである。
事件。
しかしやっぱり事件といっては大袈裟かも知れない。私は或る男と二人で酒を飲み、別段喧嘩も何も無く、そうして少くとも外見に於いては和気藹々裡に別れたというだけの出来事なのである。それでも私にはどうしてもゆるがせに出来ぬ重大事のような気がしてならぬのである。
とにかくそれは見事な男であった。あっぱれな奴であった。好いところが一つも、みじんも無かった。
私は昨年罹災してこの津軽の生家に避難して来て、ほとんど毎日神妙らしく奥の部屋に閉じこもり、時たまこの地方の何々文化会とか何々同志会とかいうところから講演しに来いまたは座談会に出席せよなどと言われる事があっても、「他にもっと適当な講師がたくさんいる筈です」と答えて断り、こっそりひとりで寝酒など飲んで寝るというやや贋隠者のあけくれにも似たる生活をしているのだけれども、それ以前の十五年間の東京生活に於いては最下等の居酒屋に出入りして最下等の酒を飲み、所謂最下等の人物たちと語り合っていたものであって、たいていの無頼漢には驚かなくなっているのである。しかしあの男には呆れた。とにかくずば抜けていやがった。
九月のはじめ、私は昼食をすませて母屋の常居という部屋でひとりぼんやり煙草を吸っていたら、野良着姿の大きな親爺が玄関のたたきにのっそり立って
「やあ」と言った。
それがすなわち問題の「親友」であったのである。
(私はこの手記に於いて、ひとりの農夫の姿を描き、かれの嫌悪すべき性格を世人に披露し、以て階級闘争に於ける所謂「反動勢力」に応援せんとする意図などは全く無いのだという事を、ばからしいけど念のために言い添えて置きたい。それはこの手記のおしまいまでお読みになったらたいていの読者には自明の事で、こんな断り書きは興覚めに違いないのであるが、ちかごろ甚だ頭の悪い無感覚の者がしきりに何やら古くさい事を言って騒ぎ立て、とんでもない結論を投げてよこしたりするので、その頭の古くて悪い(いやかえって利口なのかも知れないが)その人たちのために一言、言わでもの説明を附け加えさせていただく次第なのだ。どだいこの手記にあらわれる彼は百姓のような姿をしているけれども、決してあの「イデオロギスト」たちの敬愛の的たる農夫では無い。彼は実に複雑な男であった。とにかく私はあんな男ははじめて見た。不可解といってもいいくらいであった。私はそこに人間の新しいタイプをさえ予感した。善い悪いという道徳的な審判を私はそれに対して試みようとしているのでなく、そのような新しいタイプの予感を読者に提供し得たならばそれで私は満足なのである)
彼は、私と小学校時代の同級生であったところの平田だという。
「忘れたか」と言って白い歯を出して笑っている。その顔には幽かに見覚えがあった。
「知っている。あがらないか」私はその日、彼に対してたしかに軽薄な社交家であった。
彼は藁草履を脱いで常居にあがった。
「久しぶりだなあ」と彼は大声で言う。「何年振りだ? いや何十年振りだ? おい二十何年振りだよ。お前がこっちに来ているという事は前から聞いていたが、なかなか俺も畑仕事がいそがしくてな、遊びに来れないでいたのだよ。お前もなかなかの酒飲みになったそうじゃないか。うわっはっはっは」
私は苦笑しお茶を注いで出した。
「お前は俺と喧嘩した事を忘れたか? しょっちゅう喧嘩をしたものだ」
「そうだったかな」
「そうだったかなじゃない。これ見ろこの手の甲に傷がある。これはお前にひっかかれた傷だ」
私はその差し伸べられた手の甲を熟視したが、それらしい傷跡はどこにも無かった。
「お前の左の向う脛にもたしかに傷がある筈だ。あるだろう? たしかにある筈だよ。それは俺がお前に石をぶっつけた時の傷だ。いやよくお前とは喧嘩をしたものだ」
しかし私の左の向う脛にもまた右の向う脛にも、そんな傷は一つも無いのである。私はただあいまいに微笑してかれの話を傾聴していた。
「ところでお前に一つ相談があるんだがな。クラス会だ。どうだ、いやか。大いに飲もうじゃないか。出席者が十人として酒を二斗、これは俺が集める」
「それは悪くないけど、二斗はすこし多くないか」
「いや多くない。ひとりに二升無くては面白くない」
「しかし二斗なんてお酒が集まるか?」
「集まらないかも知れん。わからないがやってみる。心配するな。しかしいくら田舎だってこの頃は酒も安くはないんだから、お前にそこは頼む」
私は心得顔で立ち上り、奥の部屋へ行って大きい紙幣を五枚持って来て
「それじゃさきにこれだけあずかって置いてくれ。あとはまたあとで」
「待ってくれ」とその紙幣を私に押し戻し「それは違う。きょうは俺は金をもらいに来たのではない。ただ相談に来たのだ。お前の意見を聞きに来たのだ。どうせそれあ、お前からは千円くらいは出してもらわないといけない事になるだろうが、しかしきょうは相談かたがた昔の親友の顔を見たくて来たのだ。まあいいから俺にまかせてそんな金なんかひっこめてくれ」
「そうか」私は紙幣を上衣のポケットに収めた。
「酒は無いのか」と突然かれは言った。
私はさすがにかれの顔を見直した。かれも一瞬工合いの悪そうなまぶしそうな顔をしたが、しかしつっぱった。
「お前のところにはいつでも二升や三升はあると聞いているんだ。飲ませろ。かかはいないのか。かかのお酌で一ぱい飲ませろ」
私は立ち上り
「よし。じゃこっちへ来い」
つまらない思いであった。
私は彼を奥の書斎に案内した。
「散らかっているぜ」
「いやかまわない。文学者の部屋というのはみんなこんなものだ。俺も東京にいた頃いろんな文学者と附き合いがあったからな」
しかし私にはとてもそれは信じられなかった。
「やっぱりでもいい部屋だな。さすがに立派な普請だ。庭の眺めもいい。柊があるな。柊のいわれを知っているか」
「知らない」
「知らないのか?」と得意になり「そのいわれは大にして世界的小にしては家庭またお前たちの書く材料になる」
さっぱり言葉が意味をなして居らぬ。足りないのではないかとさえ思われた。しかしそうではなかった。なかなかずるくて達者な一面もあとで見せてくれたのである。
「なんだろうね、そのいわれは」
にやりと笑って
「こんど教える。柊のいわれ」ともったい振る。
私は押入れから、半分ほどはいっているウイスキイの角瓶を持ち出し
「ウイスキイだけどかまわないか」
「いいとも。かかがいないか。お酌をさせろよ」
永い間東京に住みいろんな客を迎えたけれども、私に対してこんな事を言った客はひとりも無かった。
「女房はいない」と私は嘘を言った。
「そう言わずに」と彼は私の言う事などてんで問題にせず、「ここへ呼んで来てお酌をさせろよ。お前のかかのお酌で一ぱい飲んでみたくてやって来たのだ」
都会の女、あか抜けて愛嬌のいい女、そんなのを期待して来たのならば彼にもお気の毒だし、女房もみじめだと思った。女房は都会の女ではあるが、頗る野暮ったい不器量の、そうして何のおあいそも無い女である。私は女房を出すのは気が重かった。

「いいじゃないか。女房のお酌だとかえって酒がまずくなるよ。このウイスキイは」と言いながら机の上の茶呑茶碗にウイスキイを注ぎ「昔なら三流品なんだけどでもメチルではないから」
彼はぐっと一息に飲みほし、それからちょっちょっと舌打ちをして
「まむし焼酎に似ている」と言った。
私はさらにまた注いでやりながら
「でもあんまりぐいぐいやると、あとで一時に酔いが出て来て苦しくなるよ」
「へえ? おかど違いでしょう。俺は東京でサントリイを二本あけた事だってあるのだ。このウイスキイはそうだな、六〇パーセントくらいかな? まあ普通だ。たいして強くない」と言ってまたぐいと飲みほす。なんの風情も無い。
そうしてこんどは彼が私に注いでくれて、それからまた彼自身の茶碗にもなみなみと一ぱい注いで
「もう無い」と言った。
「ああそう」と私は上品なる社交家の如く、心得顔に気軽そうに立ち、またもや押入れからウイスキイを一本取り出し栓をあける。
彼は平然と首肯してまた飲む。
さすがに私も少しいまいましくなって来た。私には幼少の頃から浪費の悪癖があり、ものを惜しむという感覚は(決して自慢にならぬ事だが)普通の人に較べてやや鈍いように思っている。けれどもそのウイスキイは謂わば私の秘蔵のものであったのである。昔なら三流品でも、しかしいまではたしかに一流品に違いなかったのである。値段も大いに高いけれども、しかしそれよりも、之を求める手蔓がたいへんだったのである。お金さえ出せば買えるというものでは無かったのである。私はこのウイスキイをかなり前にやっと一ダアスゆずってもらい、そのために破産したけれども後悔はせず、ちびちび嘗めて楽しみ、お酒の好きな作家の井伏さんなんかやって来たら飲んでもらおうとかなり大事にしていたのである。しかしだんだん無くなって、その時には押入れに二本半しか残っていなかったのである。
飲ませろと言われた時にはあいにく日本酒も何も無かったので、その残り少なの秘蔵のウイスキイを出したのであるが、しかしこんなにがぶがぶ鯨飲されるとは思っていなかった。甚だケチ臭い愚痴を言うようだが、(いや、はっきり言おう。私はこのウイスキイに関しては、ケチである。惜しいのである)まるで何か当然の事のように大威張りでぐいぐい飲まれては、さすがにいまいましい気が起らざるを得なかったのである。
それにまた、彼の談話たるやすこしも私の共感をそそってはくれないのである。それは何も私が教養ある上品な人物で相手は無学な田舎親爺だからというわけではなかった。そんな事は絶対に無い。私は全然無教養な淫売婦と、「人生の真実」とでもいったような事を大まじめで語り合った経験をさえ持っている。無学な老職人に意見せられて涙を流した事だってある。私は世に言う「学問」を懐疑さえしている。彼の談話が少しも私に快くなかったのはたしかに他の理由からである。それは何か。私はそれをここで二、三語を用いて断定するよりも、彼のその日のさまざまの言動をそのまま活写し、以て読者の判断にゆだねたほうが作者として所謂健康な手段のように思われる。
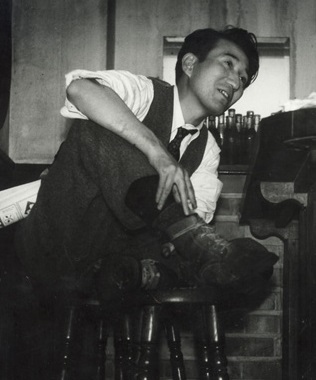
彼は「俺の東京時代は」という事をさいしょからしきりに言っていたが、酔うにしたがっていよいよ頻繁にそれが連発せられて来た。
「お前もしかし、東京では女でしくじったが」と大声で言ってにやりと笑い、「俺だって実は、東京時代にあぶないところまでいった事があるんだ。もう少しでお前と同じような大しくじりをするところまでいったんだ。本当だよ。じっさいそこまでいったんだ。しかし俺は逃げたよ。うん、逃げた。それでも女というものはいったん思い込んだ男を忘れかねると見えるな。うわっはっは。いまでも手紙を寄こすのだよ。うふふ。こないだも餅を送ってよこした。女は馬鹿なものだよまったく。女に惚れられようとしたら顔でも駄目だ、金でも駄目だ、気持だよ、心だよ。じっさい俺も東京時代はあばれたものだ。考えてみるとあの頃は無論お前も東京にいて芸者を泣かせたりなんかして遊んでいた筈だが、いちども俺と逢わなかったのは不思議だな。お前はいったいあの頃はおもにどの方面で遊んでいたのだ」
あの頃とは、私にはどの頃かわからない。それに私は東京に於いて、彼の推量の如くそんな芸者を泣かせたりして遊んだ覚えは一度だって無い。おもに屋台のヤキトリ屋で泡盛や焼酎を飲み管を巻いていたのである。私は東京に於いて、彼の所謂「女で大しくじり」をして、それも一度や二度でない、たび重なる大しくじりばかりして、親兄弟の肩身をせまくさせたけれども、しかしせめてこれだけは言えると思う、「ただ金のあるにまかせて色男ぶって、芸者を泣かせてやにさがっていたのではない!」みじめなプロテストではあるが、これをさえ私は未だに信じてもらえない立場にいるらしいのを彼の言葉に依って知らされうんざりした。
しかしその不愉快はあながちこの男に依ってはじめて嘗めさせられたものではなく、東京の文壇の批評家というもの、その他いろいろさまざま、または友人という形になっている人物に依ってさえも嘗めさせられている苦汁であるから、それはもう笑って聞き流す事も出来るようになっていたのであるが、もう一つ、この百姓姿の男が何かそれを私の大いなる弱味の如く考えているらしく、それに附け込むという気配が感ぜられて、そのような彼の心情がどうにもあさましくつまらないものに思われた。
しかしその日は私は極めて軽薄なる社交家であった。毅然たるところが一つも無かった。なんといったって私はほとんど無一物の戦災者であって、妻子を引き連れ、さほど豊かでもないこの町に無理矢理割り込ませてもらって、以てあやうく露命をつなぐを得ているという身の上に違いないのであるから、この町の昔からの住民に対してはいきおい軽薄なる社交家たらざるを得なかった。
私は母屋へ行って水菓子をもらって来て彼にすすめ、
「たべないか。くだものを食べると酔いがさめてまた大いに飲めるようになるよ」
私は彼がこの調子でぐいぐいウイスキイを飲み、いまに大酔いを発し、乱暴を働かないまでも前後不覚になっては始末に困ると思い、少し彼を落ちつかせる目的を以て、梨の皮などをむいてすすめたのである。
しかし彼は酔いを覚ます事は好まない様子で、その水菓子には眼もくれずウイスキイの茶呑茶碗にだけ手をかける。
「俺は政治はきらいだ」と突如話題は政治に飛ぶ。「われわれ百姓は政治なんて何も知らなくていいのだ。実際の俺たちの暮しに少しでも得になる事をしてくれたらそっちへつく。それでいいだろう。現物を眼の前に持って来て俺たちの手に握らせたらそっちへつく。それでいいわけではないか。われわれ百姓には野心は無いんだ。受けた恩はきっとそれだけかえしてやる。それはもうわれわれ百姓の正直なところだ。進歩党も社会党もどうだっていいんだ。われわれ百姓は田を作り畑を耕やしていたらそれでいいのだ」
私ははじめ、なぜ彼が突如としてこんな妙な事を言い出したのかわけがわからなかった。けれども次の言葉で真意が判明し苦笑した。
「しかしこないだの選挙では、お前も兄貴のために運動したろう」
「いや何も、ひとつもしなかった。この部屋で毎日自分の仕事をしていた」
「嘘だ。いかにお前が文学者で政治家でないとしてもそこは人情だ。兄貴のために大いにやったに違いない。俺はな、学問も何も無い百姓だが、しかし人情というものは持っている。俺は政治はきらいだ。野心も何も無い。社会党だの進歩党だのと言ったっておそれるところは無いと思っているのだが、しかし人情は持っている。俺はな、お前の兄貴とは別に近づきでも何でもないが、しかし少くともお前は俺と同級生でもあり親友だろう。ここが人情だ。俺は誰にたのまれなくてもお前の兄貴に一票いれた。われわれ百姓は政治も何も知らなくていい。この人情一つだけを忘れなければそれでいいと思うが、どうだ」
その一票がウイスキイの権利という事になるのだろうか。あまりにも見え透いて、私はいよいよ興覚めるばかりであった。
しかし彼だってなかなか単純な男ではない。敏感に、ふっと何か察するらしい。
「俺はしかし何も、お前の兄貴の家来になりたがっているというわけじゃないんだよ。そんなにこの俺を見下げ果ててもらっては困るよ。お前の家だって先祖をただせば油売りだったんだ。知っているか。俺は俺の家の婆から聞いた。油一合買ってくれた人には飴玉一つ景品としてやったんだ。それが当った。また川向うの斎藤だっていまこそあんな大地主で威張りかえっているけれども、三代前には川に流れている柴を拾い、それを削って串を作り、川からとった雑魚をその串にさして焼いて一文とか二文とかで売ってもうけたものなんだ。また大池さんの家なんか、路傍に桶を並べて路行く人に小便をさせて、その小便が桶一ぱいになるとそれを百姓たちに売ってもうけたのがいまの財産のはじまりだ。金持ちなんてもとをただせば皆こんなものだ。俺の一族は、いいか、この地方では一ばん古い家柄という事になっているんだ。何でも祖先は京都の人で」と言いかけて、さすがにてれくさそうにふふんと笑い、「婆の話だからあてにはならんが、とにかくちゃんとした系図は在るのだ」
私はまじめに、
「それではやはり公卿の出かも知れない」と言って彼の虚栄心を満足させてやった。
「うん、まあそれははっきりはわからないが、たいていその程度のところなのだ。俺だけはこんな汚い身なりで毎日田畑に出ているが、しかし俺の兄は、お前も知っているだろう、大学を出た。大学の野球の選手で新聞にしょっちゅう名前が出ていたではないか。弟もいま大学へはいっている。俺は感ずるところがあって百姓になったが、しかし兄でも弟でもいまではこの俺に頭があがらん。なにせ東京は食糧が無いんで、兄は大学を出て課長をしているがいつも俺に米を送ってよこせという手紙だ。しかし送るのがたいへんでな。兄が自分で取りに来たら、そうしたら俺はいくらでも背負わさせてやるんだが、やっぱり東京の役所の課長ともなれば米を背負いに来るわけにもいかんらしいな。お前だっていま何か不自由なものがあったらいつでも俺の家へ来い。俺はな、お前にただで酒を飲ませてもらおうとは思ってないよ。百姓というものは正直なもんだ。受けた恩はかならずきっちりとそれだけ返す。いや、もうお前のお酌では飲まん! かかを呼んで来い。かかのお酌でなければ、俺は飲まん!」私は一種奇妙な心持がした。別に私はそんなに彼に飲ませたいと思ってもいないのに。「もう俺は飲まんよ。かかを連れて来い! お前が連れて来なければ、俺が行って引っぱって来る。かかはどこにいるんだ。寝室か? 寝る部屋か? 俺は天下の百姓だ。平田一族を知らないかあ」次第に酔ってくだらなく騒ぎ、よろよろと立ち上る。
私は笑いながら、それをなだめて坐らせ、
「よし、そんなら連れて来る。つまらねえ女だよ。いいか」
と言って女房と子供のいる部屋へ行き、
「おい、昔の小学校時代の親友が遊びに見えているからちょっと挨拶に出てくれ」
と、もっともらしい顔をして言いつけた。

私はやはり自分の客人を女房にあなどらせたくなかった。自分のところへ来た客人が、それはどんな種類の客人でも、家の者たちにあなどられている気配が少しでも見えると、私はつらくてかなわないのだ。
女房は小さいほうの子供を抱いて書斎にはいって来た。
「このかたは僕の小学校時代の親友で平田さんというのだ。小学校時代にはしょっちゅう喧嘩して、このかたの右だか左だかの手の甲に僕のひっ掻いた傷跡がまだ残っていてね、だからきょうはその復讐においでなすったというわけだ」
「まあ、こわい」と女房は笑って言って、「どうぞよろしく」とていねいにお辞儀をした。
私たち夫婦のこんな軽薄きわまる社交的な儀礼も彼にとってまんざらでもなかったらしく、得意満面で、
「やあ、固苦しい挨拶はごめんだ。奥さん、まあこっちへずっと寄ってお酌をしてください」彼もまた抜けめのない社交家であった。蔭ではかかと呼び、めんと向えば奥さんなどと言っている。
女房のお酌でぐいと飲み、
「奥さん。いまも修治(私の幼名)に言っていたのだが、何か不自由なものがあったら俺の家へ来なさい。なんでもある。芋でも野菜でも米でも、卵でも鶏でも。馬肉はどうです、たべますか、俺は馬の皮をはぐのは名人なんだ、たべるなら取りに来なさい、馬の脚一本背負わせてかえします。雉はどうです、山鳥のほうがおいしいかな? 俺は鉄砲撃ちなんだ。鉄砲撃ちの平田といえば、このへんでは知らない者は無いんだ。お好みに応じて何でも撃ってあげますよ。鴨はどうです。鴨ならあすの朝でも田圃へ出て十羽くらいすぐ落して見せる。朝めし前に五十八羽撃ち落した事さえあるんだ。嘘だと思うなら橋のそばの鍛冶屋の笠井三郎のところへ行って聞いて見ろ。あの男は俺の事なら何でも知っている。鉄砲撃ちの平田と言えば、この地方の若い者は絶対服従だ。そうだ、あしたの晩、おい文学者、俺と一緒に八幡様の宵宮に行ってみないか。俺が誘いに来る。若い者たちの大喧嘩があるかも知れないのだ。どうもなあ、不穏な形勢なんだ。そこへ俺が飛び込んで行って、待った! と言うのだ。ちょうど幡随院の長兵衛というところだ。俺はもう命も何も惜しくねえ。俺が死んだって俺には財産があるんだからな、かかや子供は困る事がない。おい文学者。あしたの晩はぜひ一緒に行こうじゃないか。俺の偉いところを見せてやる。毎日こんな奥の部屋でまごまごしていたって、いい文学は出来ない。大いに経験をひろくしなければいけない。いったいお前はどういうものを書いているのだ。うふふ。芸者小説か。お前は苦労を知らないから駄目だ。俺はもう、かかを三度とりかえた。あとのかかほど可愛いもんだ。お前はどうだ。お前だって二人か! 三人か! 奥さんどうです、修治はあなたを可愛がるか? 俺はこれでも東京で暮した事のある男でね」
甚だまずい事になって来た。私は女房に、母屋へ行って何か酒のさかなをもらって来なさいと言いつけ、席をはずさせた。
彼は悠然と腰から煙草入れを取り出し、そうしてその煙草入れに附属した巾著の中から、ホクチのはいっている小箱だの火打石だのを出し、カチカチやって煙管に火をつけようとするのだが、なかなかつかない。
「煙草はここにたくさんあるからこれを吸い給え。煙管はめんどうくさいだろう」
と私が言うと、彼は私のほうを見てにやりと笑い、煙草入れをしまい込み、いかにも自慢そうに、
「われわれ百姓はこんなものを持っているのだよ。お前たちは馬鹿にするだろうが、しかし便利なものだ。雨の降る中でも火打石はカチカチとやりさえすれば火が出る。こんど俺は東京へ行く時、これを持参して銀座のまんなかでカチカチとやってやろうと思うんだ。お前ももうすぐ東京へ帰るのだろう? 遊びに行くよ。お前の家は東京のどこにあるのだ」
「罹災してね、どこへ行ったらいいかまだきまっていないよ」
「そうか、罹災したのか。はじめて聞いた。それじゃいろいろ特配をもらったろう。こないだ罹災者に毛布の配給があったようだが、俺にくれ」
私はまごついた。彼の真意を解するに苦しんだ。しかし彼はまんざら冗談でも無いらしく、しつこくそれを言う。
「くれよ。俺はジャンパーを作るのだ。わりにいい毛布らしいじゃないか。くれよ。どこにあるのだ。俺は帰りに持って行くぞ。これは俺の流儀でな。ほしいものがあったら、これ持って行く! と言ってもらってしまう。そのかわり、お前が俺のところへ来たらお前もそうするとよい。俺は平気だ。何を持って行ったってかまわないよ。俺はそんな流儀の男だ。礼儀だの何だのめんどうくさい事はきらいなのだ。いいか、毛布はもらって行くぞ」
そのたった一枚の毛布は、女房が宝物のように大事にしているものなのだ。所謂「立派な」家にいま住んでいるから、私たちには何でもあり余っているように彼に思われているのだろうか。私たちは、不相応の大きい貝殻の中に住んでいるヤドカリのようなもので、すぽりと貝殻から抜け出ると丸裸のあわれな虫で、夫婦と二人の子供は、特配の毛布と蚊帳をかかえて、うろうろ戸外を這いまわらなければならなくなるのだ。家の無い家族のみじめさは、田舎の家や田畠を持っている人たちにはわかるまい。このたびの戦争で家を失った人たちの大半は、(きっとそうだと思うのだが)いつか一たびは一家心中という手段を脳裡に浮べたに違いない。
「毛布はよせよ」
「ケチだなあ、お前は」
とさらにしつこくねばろうとしていた時に、女房はお膳を運んで来た。
「やあ、奥さん」と矛先はそちらに転じて、「手数をかけるなあ。食うものなんか何も要りませんから、さあここへ来てお酌をしてください。修治のお酌ではもう飲む気がしない。ケチくさくていけない。殴ってやろうか。奥さん、俺はね、東京時代にね、ずいぶん喧嘩が強かったですよ。柔道もね、ちょっと、やりました。いまだって、こんな修治みたいなのは一ひねりですよ。いつでもね、修治があなたに威張ったら俺に知らせなさい。思いきりぶん殴ってやりますから。どうです、奥さん、東京にいた時もこっちへ来てからも、修治に対して俺ほどこんな無遠慮に親しく口をきける男は無かったろう。何せ昔の喧嘩友達だから、修治も俺には気取る事が出来やしない」
ここに於いて、彼の無遠慮もあきらかに意識的な努力であった事を知るに及んで、ますます私は味気無い思いを深くした。ウイスキイをおごらせて大あばれにあばれて来たと馬鹿な自慢話の種にするつもりなのであろうか。
私はふと木村重成と茶坊主の話を思い出した。それからまた神崎与五郎と馬子の話も思い出した。韓信の股くぐりさえ思い出した。元来私は木村氏でも神崎氏でも、また韓信の場合にしても、その忍耐心に対して感心するよりは、あのひとたちがそれぞれの無頼漢に対して抱いていた無言の底知れぬ軽蔑感を考えて、かえってイヤミなキザなものしか感じる事が出来なかったのである。よく居酒屋の口論などで、ひとりが悲憤してたけり立っているのに、ひとりは余裕ありげににやにやして、あたりの人に、「こまった酒乱さ」と言わぬばかりの色目をつかい、そうしてその激昂の相手に対し、「いや、わるかったよ、あやまるよ、お辞儀をします」など言ってるのを見かけることがあるけれども、あれはまことにイヤミなものである。卑怯だと思う。あんな態度に出られたら、悲憤の男はさらに物狂おしくあばれ廻らざるを得ないだろうと思われる。木村氏や神崎氏、または韓信などは、さすがにそんな観衆に対していやらしい色眼をつかい、「わるかったよ、あやまるよ」の露骨なスタンドプレイを演ずる事なく、堂々と、それこそ誠意おもてにあらわれる態の詫び方をしたに違いないが、しかしそれにしても之等の美談は私のモラルと反撥する。私はそこに忍耐心というものは感ぜられない。忍耐とはそんな一時的なドラマチックなものでは無いような気がする。アトラスの忍耐、プロメテの忍苦、そのようなかなり永続的な姿であらわされる徳のように思われる。しかも前記三氏の場合、その三偉人はおのおの、その時、奇妙に高い優越感を抱いていたらしい節がほの見えて、あれでは茶坊主でも馬子でもぶん殴りたくなるのももっともだと、かえってそれらの無頼漢に同情の心をさえ寄せていたのである。殊に神崎氏の馬子など、念入りに詫び証文まで取ってみたが、いっこうに浮かぬ気持で、それから四、五日いよいよ荒んでやけ酒をくらったであろうと思われる。そのように私は元来、あの美談の偉人の心懐には少しも感服せず、かえって無頼漢どもに対して大いなる同情と共感を抱いていたつもりであったが、しかしいま眼前にこの珍客を迎え、従来の私の木村神崎韓信観に重大なる訂正をほどこさざるを得なくなって来たようであった。
卑怯だって何だってかまわない。荒れ馬は避くべしというモラルに傾きかけて来たのである。忍耐だの何だの、そんな美徳について思いをひそめている余裕は無い。私は断言する。木村神崎韓信は、たしかにあのやけくその無頼の徒より弱かったのだ、圧倒せられていたのだ。勝目が無かったのだ。キリストだって、時われに利あらずと見るや、「かくして主は、のがれ去り給えり」という事になっているではないか。
のがれ去るより他は無い。いまここでこの親友を怒らせ、戸障子をこわすような活劇を演じたら、これは私の家では無し、甚だ穏やかでない事になる。そうでなくても、子供が障子を破り、カーテンを引きちぎり、壁に落書などして、私はいつも冷や冷やしているのだ。ここは何としてもこの親友の御機嫌を損じないように努めなければならぬ。あの三氏の伝説は、あれは修身教科書などで「忍耐」だの「大勇と小勇」だのという題でもってあつかわれているから、われら求道の人士をこのように深く惑わす事になるのである。私がもしあの話を修身の教科書に採用するとしたなら、題を「孤独」とするであろう。
私はいまこそあの三氏のあの時の孤独感を知ったと思った。
彼の気焔を聞きながら、私はひそかにそのような煩悶をしているうちに、突如彼は、
「うわあっ!」というすさまじい叫声を発した。
ぎょっとして彼を見ると、彼は、
「酔って来たあっ!」と喚き、さながら仁王の如く、不動の如く、眼を固くつむってううむと唸って、両腕を膝につっぱり、満身の力を発揮して酔いと闘っている様子である。
酔う筈である。ほとんど彼ひとりで、すでに新しい角瓶の半分以上もやっているのだ。額には油汗がぎらぎら浮いて、それはまことに金剛あるいは阿修羅というような形容を与えるにふさわしい凄まじい姿であった。私たち夫婦はそれを見て実に不安な視線を交したが、しかし三十秒後には彼はけろりとなり、
「やっぱりウイスキイはいいな。よく酔う。奥さん、さあお酌をしてくれ。もっとこっちへ来なさいよ。俺はね、どんなに酔っても正気は失わん。きょうはお前たちのごちそうになったが、こんどは是非ともお前たちにごちそうする。俺のうちに来いよ。しかし俺の家には何も無いぞ。鶏は養ってあるが、あれは絶対につぶすわけにいかん。ただの鶏じゃないのだ。シャモと言ってな、喧嘩をさせる鶏だ。ことしの十一月にシャモの大試合があって、その試合に全部出場させるつもりでただいま訓練中なんだが、ぶざまな負けかたをしたやつだけをひねりつぶして食うつもりだ。だから十一月まで待つんだね。まあ大根の二、三本くらいはあげますよ」だんだん話が小さくなって来た。「酒も無い、何も無い。だからこうして飲みに来たんだ。鴨一羽、そのうち、とったら進呈するがね、しかしそれには条件がある。その鴨を俺と修治と奥さんと三人で食って、その時に修治はウイスキイを出して、そうしてその鴨の肉をだな、まずいなんて言ったら承知しねえぞ。こんなまずいものなんて言ったら承知しねえ。俺がせっかく苦心して撃ちとった鴨だ。おいしいと言ってもらいたい。いいか約束したぞ。おいしい! うまい! と言うのだぞ。うわっはっはっは。奥さん、百姓というものはこういうものだ。馬鹿にされたらもう縄きれ一本だってくれてやるのはいやだ。百姓とつき合うにはこつがある。いいか、奥さん。気取ってはいかん、気取っては。なあに、奥さんだって、俺のかかと同じ事で、夜になれば、……」
女房は笑いながら、
「子供が奥で泣いているようですから」
と言って逃げてしまった。
「いかん!」と彼は呶鳴って立ち上り、「お前のかかは、いかん! 俺のかかはあんなじゃないよ。俺が行ってひっぱって来る。馬鹿にするな。俺の家庭はいい家庭なんだ。子供は六人あるが夫婦円満だぞ。嘘だと思うなら橋のそばの鍛冶屋の三郎のところへ行って聞いてみろ。かかの部屋はどこだ。寝室を見せろ。お前たちの寝る部屋を見せろよ」
ああ、このひとたちに大事なウイスキイを飲ませるのはつまらん事だ!
「よせ、よせ」私も立ち上って彼の手をとり、さすがに笑えなくなって、「あんな女を相手にするな。久し振りじゃないか。たのしく飲もう」
彼はどたりと腰を下し、
「お前たちは夫婦仲が悪いな? 俺はそうにらんだ。へんだぞ。何かある。俺はそうにらんだ」
にらむもにらまぬも無い。その「へん」な原因は親友の滅茶な酔い方に在るのだ。
「面白くない。ひとつ歌でもやらかそうか」
と彼が言ったので私は二重に、ほっとした。
一つには、歌に依ってこの当面の気まずさが解消されるだろうという事と、もう一つは、それは私の最後のせめてもの願いであったのだが、とにかく私はお昼からそろそろ日が暮れて来るまで五、六時間も、この「全く附き合いの無かった」親友の相手をしていろいろと彼の話を聞き、そのあいだほんの一瞬たりともこの親友を愛すべき奴だとも、また偉い男だとも思う事が出来ず、このままわかれては私は永遠にこの男を恐怖と嫌悪の情だけで追憶するようになるだろうと思うと、彼のためにも私のためにもこんなつまらない事はない、一つだけでいい、何か楽しくなつかしい思い出になる言動を示してくれ、どうかわかれ際にかなしい声で津軽の民謡か何か歌って私を涙ぐませてくれという願望が、彼の歌をやらかそうという動議に依ってむらむらと胸中に湧き起って来たのである。
「それあいい。ぜひ一つたのむ」
それはもはや軽薄なる社交辞令ではなかった。私はしんからそれ一つに期待をかけた。
しかしその最後のものまでむざんに裏切られた。
山川草木うたたあ荒涼
十里血なまあぐさあし新戦場
しかも後半は忘れたという。
「さ、帰るぞ、俺は。お前のかかには逃げられたし、お前のお酌では酒がまずいし、そろそろ帰るぞ」
私は引きとめなかった。
彼は立ち上って、まじめくさり、
「クラス会は、それじゃ仕方が無い、俺が奔走してやるからな、後はよろしくたのむよ。きっと面白いクラス会になると思うんだ。きょうはごちそうになったな。ウイスキイはもらって行く」
それは覚悟していた。私は四分の一くらいはいっている角瓶に、彼がまだ茶呑茶碗に飲み残して在るウイスキイを注ぎ足してやっていると、
「おい、おい。それじゃないよ。ケチな真似をするな。新しいのがもう一本押入れの中にあるだろう」
「知っていやがる」私は戦慄し、それからいっそ痛快になって笑った。あっぱれというより他は無い。東京にもどこにもこれほどの男はいなかった。
もうこれで井伏さんが来ても誰が来ても共にたのしむ事が出来なくなった。私は押入れから最後の一本を取り出して彼に手渡し、よっぽどこのウイスキイの値段を知らせてやろうかと思った。それを言っても彼は平然としているか、またはそれじゃ気の毒だから要らないと言うかちょっと知りたいと思ったがやめた。ひとにごちそうしてその値段を言うなどやっぱり出来なかった。
「煙草は?」と言ってみた。
「うむ、それも必要だ。俺は煙草のみだからな」
小学校時代の同級生とは言っても、私には五、六人の本当の親友はあったけれども、しかしこのひとに就いての記憶はあまり無いのだ。彼だってその頃の私に就いての思い出は、そのれいの喧嘩したとかいう事の他にはほとんど無いのではあるまいか。しかもたっぷり半日、親友交歓をしたのである。私には強姦という極端な言葉さえ思い浮んだ。
けれどもまだまだこれでおしまいでは無かったのである。さらに有終の美一点が附加せられた。まことに痛快とも小気味よしとも言わんかた無い男であった。玄関まで彼を送って行きいよいよわかれる時に、彼は私の耳元で烈しくこう囁いた。
「威張るな!」
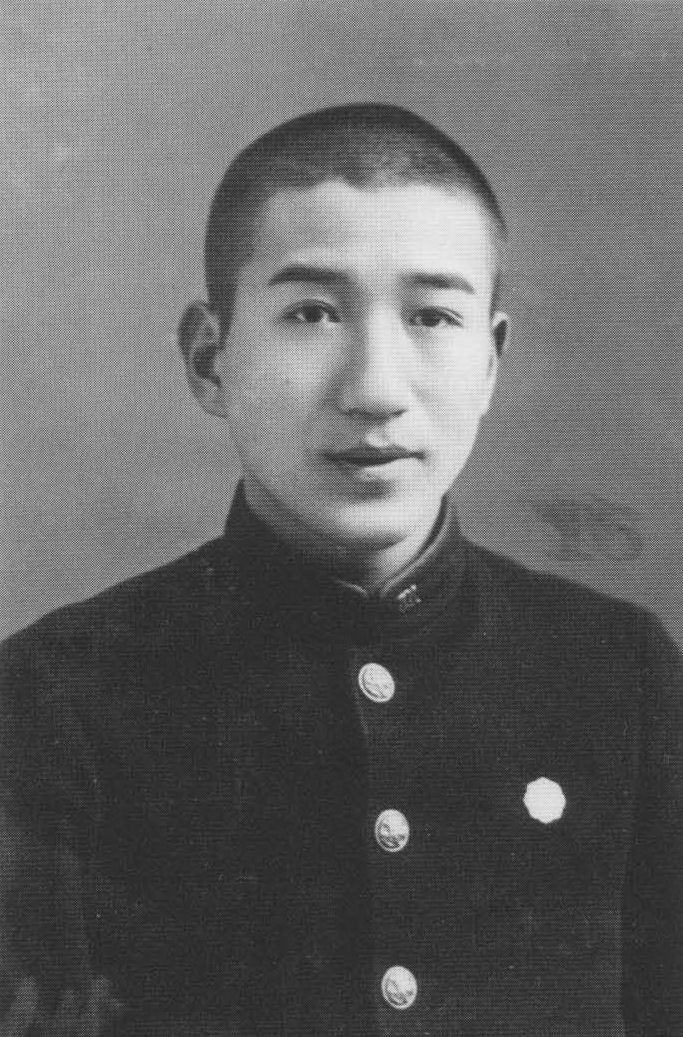
以上をその知人に読ませたら、「太宰はあの読点の打ち方あっての太宰だと、改めて思った」などとうそぶいてる。なんだい。ま、確かに読点を減らして淀みなくなると、どうも太宰っぽさが薄まる。すんなり読めればいいものではないよなと、自分でこんな試みをやっておきながら結果的に再認識することになった。「太宰っぽさ」の秘密の一端は、読点の打ち方にあるのかもしれない。

